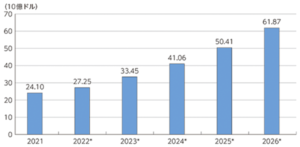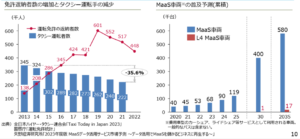2025年4月、アメリカのアルファベット傘下の自動運転企業「ウェイモ」が日本に上陸しました。*6
タクシーアプリを展開するGO、東京最大手のタクシー会社である日本交通とパートナーシップを締結しての参入です。
ただすぐに運行するわけではありません。まずは自動運転技術を東京の公道に適応させるために、4月中旬から日本交通の乗務員が運転するウェイモの自動運転車両を、港区、新宿区、渋谷区、千代田区、中央区、品川区、江東区でテスト走行しつつ、さまざまなデータを収集しています。
ウェイモの車両が搭載する完全自動運転システムWaymo Driverは、AIと一連のセンサーを利用して、人が運転席にいなくても自動車を安全に走行させることができます。*7

図4 Waymo Drive
出所)Waymo Japan「新たな旅を、東京で」
https://waymo.com/intl/jp/waymo-in-japan/
Waymo Driverによるサービスを新たなエリアで開始する前には、その地域を詳細にマッピングする必要があります。マッピングはレーンマーク、一時停止標識、縁石、横断歩道まで細部にわたります。*8
こうして作成したオリジナルの地図を、リアルタイムでのセンサーデータとAIによるデータと比較することで、常に正確な位置を把握します。
ウェイモは現在、サンフランシスコやロサンゼルス、フェニックス、オースティンなどの合計1,200平方キロメートルを超える人口密度の高い都市で、毎週160万キロメートル以上走行し、数十万組もの顧客にサービスを提供しています。*7
ウェイモは、運行している都市で、人間が運転する場合と比べて負傷を伴う衝突を78%削減したと発表していますが、事故が皆無というわけではありません。これまで、道路上のチェーンやゲート、電信柱などの障害物との軽微な衝突が発生し、その度に自動運転車両をリコールしてソフトウェアをアップデートしています。*9